※本ページはプロモーションが含まれています。
就職や転職で「資格は必要?」と悩んでいませんか?
実は、職種によって資格の重要性は大きく異なり、必須の場合もあれば不要な場合もあります。
本記事では、資格が必要な職種と不要な職種、就活で役立つ資格を詳しく解説します。
自分のキャリアに本当に必要な資格を見極めて、効率的な就職・転職活動を進めましょう。
就職・転職に資格は必要?

就職・転職における資格の必要性は、目指す職種や業界によって大きく異なります。
以下で詳しく解説します。
資格が必須の職種も多い
専門性の高い分野では、資格が必須となる職種が数多く存在します。
例えば、医師や看護師、弁護士、建築士などは資格がなければその職業に就くことができません。
これらの職種では、資格は単なる知識の証明ではなく、法的に業務を行うための必要条件となっています。
また、不動産業界の宅地建物取引士のように、事業所に一定数の有資格者を配置することが法律で義務付けられているケースもあります。
このような職種を目指す場合は資格取得は避けて通れない道であり、計画的な学習と準備が必要です。
「未経験OK」でも資格保有者が有利な理由
求人に「未経験OK」と記載されていても、実際の選考では資格保有者が有利になることが多いのが実情です。
資格は、その分野に対する基礎知識があることの客観的な証明となり、企業側の教育コストを削減できるというメリットがあるからです。
例えば、経理職の求人で簿記資格保有者は、基本的な会計知識を持っていることが保証されるため、即戦力に近い形で業務に入れます。
また、資格取得の過程で身につけた学習意欲や向上心も評価されるポイントで、特に応募者が多い人気企業では、資格が最初の選考段階でのふるい分けの基準になることもあります。
ただし、資格はあくまでもプラスアルファの要素であり、コミュニケーション能力や人柄も重要な判断基準となることを忘れてはいけません。

実務経験と資格、どちらが重視される?
実務経験と資格のどちらが重視されるかは、職種や企業の方針によって異なりますが、一般的には実務経験の方が高く評価される傾向があります。
特に中途採用では、即戦力として活躍できる実務経験者が求められることが多く、資格は補完的な要素として見られることが一般的です。
しかし、未経験者や第二新卒の場合は、資格が実務経験の不足を補う重要な要素となります。
また、専門性の高い分野では、実務経験と資格の両方が求められるケースも少なくありません。
理想的なのは、実務経験を積みながら関連資格を取得し、両方を武器にしてキャリアアップを図ることです。
「資格は必要ない」と言われる理由は?

資格が必要ないと言われることもありますが、その背景にはいくつかの理由があります。
なぜそのような意見があるのか、具体的に確認していきましょう。
実務スキルや経験が重視されるケースがあるから
IT業界のエンジニアやWebデザイナー、営業職など、実務スキルや経験が資格以上に重視される職種では、「資格は必要ない」という意見が多く聞かれます。
例えば、プログラマーの場合、情報処理技術者資格を持っているよりも、GitHubで公開している実際のコードや、開発したアプリケーションの方が採用担当者の注目を集めます。
また、変化の速い業界では資格の内容が実務に追いついていないケースもあり、最新の技術やトレンドに対応できる柔軟性のほうが重要視されます。
ただし、これは資格が全く無意味ということではなく、基礎知識の証明として一定の価値はあることを理解しておく必要があります。
難易度の低い資格だから
合格率が高く、短期間で取得できる資格については、「就職・転職にあまり意味がない」という評価を受けることがあります。
これは、誰でも簡単に取得できる資格では、ほかの応募者との差別化が図れないためです。
例えば合格率80%を超えるような資格は、基礎知識の確認程度の位置づけとなり、採用の決め手にはなりにくいのが現実です。
また、通信講座で数週間勉強すれば取得できるような資格も、専門性のアピールとしては弱いと見なされがちです。
企業側も資格の難易度や価値を理解しているため、簡単な資格をいくつも並べるよりも、難関資格を一つ取得する方が評価されやすいでしょう。
ただし、入門資格として基礎を固める意味では価値があるため、ステップアップの第一歩として活用することは有効です。
実務に直結しない資格だから
資格の内容が実際の業務とかけ離れている場合「資格は必要ない」と判断されることがあります。
例えば、理論中心の資格で実践的なスキルが身につかないものや、古い知識体系に基づいた資格などは、現場では役立たないと評価されがちです。
また、一般教養的な資格や趣味の延長のような資格も、専門職への就職には直接的な効果が期待できません。
資格を選ぶ際は、目指す職種の実務内容をよく研究し、本当に必要とされる知識やスキルが身につく資格かどうかを見極めることが重要です。
資格取得を自己満足で終わらせないためにも、実務との関連性を常に意識しておく必要があります。
資格が必要な代表的職種

特定の資格がなければ就けない職種や、資格保有者が有利となる職種があります。
代表的な職種とその資格について詳しく紹介するので、ぜひ参考にしてください。
税理士
| 資格名 | 税理士 |
|---|---|
| 受験資格 | 会計学科目:なし 税法科目:あり(学歴・資格・職歴のいずれかを満たす) |
| 試験頻度 | 年に1回(8月) |
| 難易度(合格率) | 10~15%前後 |
| 勉強時間目安 | 5,000〜10,000時間 |
| 公式サイト | https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/zeirishi.htm |
税理士は税務相談、税務申告書の作成、税務調査の立会いなど、税金に関する専門的な業務を独占的に行える国家資格です。
企業や個人事業主の税務をサポートし、適正な納税と節税対策を指導する重要な役割を担います。
税理士資格を取得するには、簿記論と財務諸表論の2科目に加え、所得税法や法人税法などの税法科目から3科目、合計5科目に合格する必要があります。
平均合格率は各科目10〜20%程度と難関ですが、科目合格制のため、働きながら段階的に取得することも十分に可能です。
なお、実務経験2年以上が登録要件となるため、会計事務所での実務経験を積みながら資格取得を目指すケースが一般的です。
社会保険労務士
| 資格名 | 社会保険労務士 |
|---|---|
| 受験資格 | あり (学歴・実務経験・厚生労働大臣の認めた国家試験合格 のいずれかを満たす) |
| 試験頻度 | 年に1回(8月) |
| 難易度(合格率) | 6~7%前後 |
| 勉強時間目安 | 1,000時間 |
| 公式サイト | https://www.sharosi-siken.or.jp/ |
社会保険労務士(社労士)は労働保険や社会保険の手続き、就業規則の作成、労務管理のコンサルティングなど、企業の人事労務分野で活躍する専門資格です。
試験は年1回実施され、合格率は6〜7%程度と狭き門ですが、独占業務があることから資格の価値は非常に高いです。
企業の人事部門での勤務はもちろん、独立開業して複数の企業と顧問契約を結ぶことも可能です。
特に中小企業では、専門の人事部門を持たないケースが多いため、外部の社労士に依頼することが一般的で、安定した需要が見込めます。
労働問題への関心の高まりとともに、今後もますます重要性が増していく資格といえるでしょう。
中小企業診断士
| 資格名 | 中小企業診断士 |
|---|---|
| 受験資格 | 1次試験:なし 2次試験(筆記):1次試験合格者 2次試験(口述):筆記試験合格者 |
| 試験頻度 | 年1回 |
| 難易度(合格率) | 4~5% |
| 勉強時間目安 | 1,000~1,200時間 |
| 公式サイト | https://www.jf-cmca.jp/ |
中小企業診断士は、中小企業の経営課題を診断し、改善策を提案する経営コンサルタントの国家資格です。
経営戦略、マーケティング、財務、人事など、経営全般の幅広い知識が求められ、「ビジネスパーソンが取得したい資格」の上位に常にランクインしています。
1次試験(7科目)と2次試験(筆記・口述)に合格し、実務補習または診断実務を経て登録が可能となります。
合格率は1次・2次を通じて4〜5%程度と難関ですが、体系的な経営知識が身につくため、コンサルタントとしての独立だけでなく、企業内での経営企画や事業開発部門でも高く評価されます。
また、公的な中小企業支援機関での専門家登録も可能で、安定した収入源を確保しながら経験を積むこともできます。
行政書士
| 資格名 | 行政書士 |
|---|---|
| 受験資格 | なし |
| 試験頻度 | 年に1回(11月第2日曜日) |
| 難易度(合格率) | 10~15%前後 |
| 勉強時間目安 | 800~1,000時間 |
| 公式サイト | https://gyosei-shiken.or.jp/ |
行政書士は官公署に提出する書類の作成や、許認可申請の代理業務を行う国家資格です。
会社設立、建設業許可、飲食店営業許可、在留資格申請など、扱える書類は1万種類以上にのぼり、幅広い分野で活躍できます。
法律系資格の中では比較的取得しやすいとされていますが、民法や行政法などの専門知識が必要となります。
独立開業しやすい資格として人気が高く、自宅を事務所として低コストで開業することも可能で、特に外国人の在留資格関連業務は需要が拡大しており、専門分野を持つことで差別化を図れます。
社労士や税理士など、ほかの士業資格と組み合わせることで、より幅広いサービスを提供できるようになり、ビジネスチャンスが広がります。
宅建士
| 資格名 | 宅地建物取引士 |
|---|---|
| 受験資格 | なし |
| 試験頻度 | 年に1回(10月第3日曜日) |
| 難易度(合格率) | 13~18%程度 |
| 勉強時間目安 | 400~600時間 |
| 公式サイト | https://www.retio.or.jp/exam/ |
宅地建物取引士(宅建士)は、不動産取引における重要事項の説明や契約書への記名押印など、不動産取引の専門家として欠かせない国家資格です。
不動産業を営む事務所では、従業員5人に1人以上の割合で宅建士を設置することが法律で義務付けられており、不動産業界では必須の資格となっています。
資格手当が支給される企業も多く、月額1〜3万円程度の収入アップが期待できます。
また、独立して不動産仲介業を開業する道も開かれており、成功すれば高収入も夢ではありません。
看護師・医療系資格
看護師をはじめとする医療系資格は、人の生命に関わる業務を行うため、国家資格の取得が必須となっています。
例えば、看護師は看護専門学校や大学で学んだ後に、国家試験に合格する必要があります。
医療系資格の強みは全国どこでも需要があり、安定した雇用が期待できることです。
高齢化社会の進展により、医療・介護分野の人材需要は今後も増加が見込まれ、資格取得への投資価値は非常に高いといえるでしょう。
就活・転職に役立つおすすめ資格

必須ではないものの、就職・転職で有利に働く汎用性の高い資格があります。
幅広い職種で評価される資格を紹介しますので、ぜひチェックしてください。
日商簿記2級
| 資格名 | 日商簿記検定 |
|---|---|
| 受験資格 | なし |
| 試験頻度 | 随時実施 |
| 難易度 | 3級:30~50%前後 2級:20~30%前後 |
| 勉強時間目安 | 3級:100~150時間 2級:250~300時間 |
| 公式サイト | https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping |
日商簿記2級は、企業の経理部門や事務職を目指す人にとって非常に有効な資格です。
商業簿記と工業簿記の両方を学ぶことで、製造業を含むあらゆる企業の会計処理に対応できる知識が身につきます。
経理職の求人では「簿記2級以上」を応募条件とする企業が多く、資格の有無が選考の分かれ目となることも少なくありません。
営業職や企画職でも、財務諸表を読み解く力は強みとなり、キャリアの幅を広げてくれるでしょう。
将来的に経理のスペシャリストを目指すなら、簿記1級や税理士へのステップアップも視野に入れることができ、明確なキャリアパスを描ける点も魅力です。

FP2級
| 資格名 | FP(ファイナンシャルプランナー) |
|---|---|
| 受験資格 | 3級:誰でも受験可 2級:FP3級の合格者など 1級:FP2級合格後、1年以上のFP実務経験など |
| 試験頻度 | 2・3級:通年実施、1級:年に3回 |
| 難易度(合格率) | FP3級:約85% FP2級:約45~55% FP1級:約10%(日本FP協会) |
| 勉強目安時間 | FP3級:30~150時間 FP2級:200~300時間 FP1級:450~600時間 |
| 公式サイト | 日本FP協会:https://www.jafp.or.jp/exam/ 金融財政事情研究会:https://www.kinzai.or.jp/ |
ファイナンシャル・プランナー(FP)2級以上の資格は保険・金融業界はもちろん、不動産業界や一般企業の営業職でも高く評価されます。
ライフプランニング、リスク管理、金融資産運用、税金、不動産、相続など、お金に関する幅広い知識を体系的に学べるため、顧客への提案力が格段に向上します。
また、独立系FPとして起業する道もあり、個人のライフプラン相談やセミナー講師として活躍することも可能です。
お金の知識は自分自身の生活設計にも役立つため、取得して損のない資格といえるでしょう。
基本情報技術者
| 資格名 | 基本情報技術者 |
|---|---|
| 受験資格 | なし |
| 試験頻度 | 随時実施 |
| 難易度(合格率) | 40~50%前後 |
| 勉強時間目安 | 150~200時間 |
| 公式サイト | https://www.ipa.go.jp/shiken/kubun/fe.html |
基本情報技術者試験は、IT業界を目指す人だけでなく、あらゆる職種でデジタル化が進む現代において価値のある資格です。
コンピュータの基礎知識、プログラミング、ネットワーク、セキュリティ、プロジェクトマネジメントなど、ITに関する幅広い知識を証明できます。
IT企業のエンジニアやプログラマーはもちろん、一般企業のシステム部門、DX推進部門でも評価される資格です。
今後ますますIT化が進む中で、文系・理系を問わず持っていて損のない資格といえるでしょう。
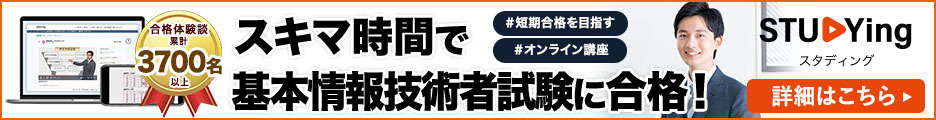
TOEIC
| 資格名 | TOEIC |
|---|---|
| 受験資格 | なし |
| 試験頻度 | 毎月1回 |
| 難易度(合格率) | 得点によって異なる |
| 勉強時間目安 | 得点によって異なる |
| 公式サイト | https://www.iibc-global.org/toeic.html |
TOEICは、ビジネス英語力を測る試験として、多くの企業が採用や昇進の基準として活用しています。
特に600点以上のスコアは履歴書に記載する価値があり、730点以上なら英語を使う部署への配属も視野に入ります。
外資系企業や海外展開している日本企業では、800点以上を求められることも珍しくありません。
TOEICの利点は合否ではなくスコアで評価されるため、段階的に実力を向上させられることです。
グローバル化が進む中、英語力は業界・職種を問わず重要なスキルとなっており、高スコアは確実にキャリアの選択肢を広げてくれるでしょう。
キャリアコンサルタント
| 資格名 | キャリアコンサルタント |
|---|---|
| 受験資格 | ・厚生労働大臣認定の講習を修了 ・実務経験3年以上 ・学科試験または実技試験の合格者 ※上記いずれかを満たす |
| 試験頻度 | 年3回(3月・7月・11月) |
| 難易度(合格率) | 学科:約65%/実技:約60% 両方合格:約50% |
| 勉強時間目安 | 約200時間 |
| 公式サイト | https://www.career-shiken.org/ |
キャリアコンサルタントは、2016年に国家資格となった比較的新しい資格で、個人のキャリア形成を支援する専門家として注目されています。
企業の人事部門、人材紹介会社、大学のキャリアセンター、ハローワークなどで需要があり、働き方改革の推進により企業内でのニーズも高まっています。
独立してキャリア相談室を開業したり、セミナー講師として活動したりすることも可能です。
人の成長を支援することにやりがいを感じる人にとって、社会貢献度の高い魅力的な資格といえるでしょう。
資格がなくても活躍できる職種は?

すべての職種で資格が必要なわけではありません。
実力や経験が重視される職種について解説しますので、確認してみましょう。
営業職
営業職は、資格よりもコミュニケーション能力や人間性が重視される代表的な職種です。
顧客のニーズを的確に把握し、信頼関係を構築しながら商品やサービスを提案する力が求められます。
ただし、扱う商品によっては専門知識が必要な場合もあり、不動産営業なら宅建士、金融商品営業ならFP資格があると有利になることもあります。
しかし、これらはあくまでプラスアルファの要素であり、基本的には人柄、熱意、粘り強さ、提案力などの個人の資質が成功の鍵となります。
未経験からでも始めやすく成果を出せば高収入も期待できるため、資格にとらわれずチャレンジできる職種といえるでしょう。
接客・販売職
接客・販売職も、資格よりも実践的なスキルや接客態度が重視される職種です。
お客様に対する気配り、商品知識、売り場づくりのセンスなど、現場で培われる能力が評価の中心となります。
アパレル、飲食、小売など、業界によって求められるスキルは異なりますが、共通して重要なのは「お客様を大切にする心」です。
接客経験を積めば、店長やエリアマネージャーへのキャリアアップも可能で、人と接することが好きな人にとって、資格に縛られずに活躍できる魅力的な職種です。
なお、販売士検定を取得しておくと面接でアピールできるでしょう。

私はこのテキスト・問題集で一発合格しました!
クリエイティブ系
Webデザイナー、グラフィックデザイナー、動画クリエイター、ライターなどのクリエイティブ系職種では、資格よりも作品の質と実績が評価の中心となります。
採用選考では、過去の作品をまとめたポートフォリオの提出が求められ、技術力やセンス、独創性が判断されます。
デザイン系の資格や検定も存在しますが、実際の現場では最新のトレンドを取り入れた作品や、クライアントの課題を解決した実績のほうが説得力を持ちます。
独学やオンラインスクールで技術を身につけ、実際に作品を作りながらスキルを磨いていくことが一般的です。
フリーランスとして独立しやすい職種でもあり、実力次第で高収入も期待できる、資格に依存しない実力主義の世界といえるでしょう。
就職の観点からあまり必要とされていない資格は?

取得しても就職・転職にあまり効果が期待できない資格もあります。
時間と費用を無駄にしないよう、事前にチェックしておきましょう。
秘書検定
秘書検定はビジネスマナーや接遇、文書作成などの知識を体系的に学べる資格ですが、就職・転職市場での評価はそれほど高くないでしょう。
ただし、検定で学ぶビジネスマナーや敬語の使い方、来客対応などの知識は、あらゆる職種で活用できる基礎スキルです。
新卒の就活では、社会人としての基礎があることのアピールにはなりますが、中途採用では実務経験のほうが重視されます。
取得するなら、あくまでも自己啓発の一環として、他の専門資格と組み合わせることで価値を高めることをおすすめします。
整理収納アドバイザー
整理収納アドバイザーは、片付けや収納のノウハウを学べる民間資格として人気がありますが、これだけで就職・転職が有利になることはほとんどありません。
2級は1日の講座受講で取得でき、合格率もほぼ100%のため、資格としての希少性は低いといえます。
インテリアコーディネーターや建築士など、住宅関連の専門資格と組み合わせることで付加価値を生み出すことは可能ですが、単独での就職効果は期待できないでしょう。
趣味や自己啓発として取得する分には良いですが、キャリアアップを目的とするなら他の資格を優先するのもおすすめです。
MOS(Word/Excel)
MOS(Microsoft Office Specialist)は、WordやExcelの操作スキルを証明する資格ですが、現代のビジネスシーンでは「できて当たり前」のスキルとなっているため、就職・転職での差別化要因にはなりにくいでしょう。
特に若い世代では、基本的なPC操作は習得済みと見なされることが多く、資格の有無はあまり重視されません。
合格率も高く、短期間で取得可能なため、専門性のアピールとしては弱いといえます。
ただし、事務職への転職で実務経験がない方や長期間のブランクがある場合は、最低限のPCスキルがあることの証明として一定の価値はあります。
より高度なExcelスキル(VBA、ピボットテーブル、マクロなど)を実務で活用できるレベルまで身につければ、データ分析職などで評価される可能性もあります。
FP3級
FP3級は、ファイナンシャル・プランニングの入門資格として人気がありますが、合格率が70〜80%と非常に高いため、就職・転職でのアピール材料としては弱いといえます。
学習内容は生活に役立つ知識ばかりで、自己啓発としては価値がありますが、専門性の証明にはなりません。
もしFP資格でキャリアアップを目指すなら、最初から2級を目標に据えて学習することをおすすめします。
資格が必要かどうかを見極める判断軸

資格を取得するには、時間もお金もかかります。
本当に必要な資格かどうか、以下の判断軸で見極めてから学習を始めましょう。
目指す職種・働き方にマッチしているか
資格を取得する前に最も重要なのは、その資格が目指す職種や働き方に本当に必要かどうかを見極めることです。
例えば、経理職を目指すなら簿記資格は必須に近いですが、営業職を目指すのに簿記資格を取得しても直接的な効果は限定的です。
まずは希望する職種の求人情報を複数チェックし、どんな資格が求められているか、必須条件なのか歓迎条件なのかを確認しましょう。
独立を視野に入れているなら、独占業務のある資格を優先的に検討すべきでしょう。
明確な目的意識を持って資格を選ぶことで、学習のモチベーションも維持しやすくなります。
無理なく取得できそうか
資格の必要性が確認できても、現実的に取得可能かどうかを冷静に判断することが大切です。
まず、学習時間の目安を調べ、現在の生活スタイルの中で確保できるか検討しましょう。
受験費用やテキスト代、スクール費用などトータルでかかる費用も事前に把握し、経済的に無理がないか確認しておくと安心です。
難関資格に挑戦する場合は、段階的にステップアップできる関連資格から始めることも検討すべきです。
無理な計画は挫折につながるため、「少し頑張れば達成できる」レベルの目標設定が成功の秘訣です。
今後も需要のある資格かどうか
資格を選ぶ際は、将来性も重要な判断基準となります。
技術の進歩やAIの発展により、一部の資格や職種の需要が減少する可能性があることを考慮すべきです。
単純な事務処理系の資格は業務自動化の影響を受けやすいですが、人間にしかできない判断や対人スキルが必要な資格、法的な責任を伴う資格は今後も安定した需要が見込めます。
業界団体の動向や資格保有者数の推移、求人数の変化なども参考にしながら、5年後、10年後も価値を持ち続ける資格かどうかを見極めることが大切です。
せっかく時間と費用をかけて取得するなら、長期的にキャリアの武器となる資格を選びましょう。
まとめ
就職・転職における資格の必要性は、目指す職種によって大きく異なります。
医療・法律・建築などの専門職では資格が必須ですが、営業職やクリエイティブ職では実務経験や実績のほうが重視されます。
資格取得を検討する際は目指すキャリアとの関連性、取得の現実性、将来性の3つの観点から慎重に判断することが重要です。
「とりあえず資格を取る」のではなく、明確な目的を持って必要な資格を選び、計画的に取得することで、効果的なキャリアアップが実現できるでしょう。
資格はあくまでも手段であり、最終的には実務で成果を出すことが大切だということを忘れずに、バランスの取れたスキルアップを目指しましょう。


